はじめに
「気づけばスマホを触りながら食事」「動画を見ながら勉強」——こんな“ながらスマホ”の習慣、ありませんか?
一見、時間を有効活用しているように思えて、実は脳に大きな負担を与えています。
この記事では、なぜ“ながらスマホ”が脳疲労を招くのか、その仕組みとやめ方の具体的なステップを解説します。
ながらスマホが脳疲労を招く理由
1. 脳は同時処理が苦手
脳科学の研究によれば、人間の脳はマルチタスクに向いていません。
「ご飯を食べながらSNSチェック」や「音楽を聴きながらメール返信」などは、実際には高速で注意を切り替えている状態です。
この切り替えが繰り返されることで、脳は余分なエネルギーを消耗し、疲労が蓄積してしまいます。
2. 情報過多によるストレス
SNSやニュースアプリは常に新しい情報を提供します。食事や作業と同時に取り込むことで、消化活動や集中の妨げとなり、無意識のストレスを増大させます。
3. 睡眠の質を下げる
特に就寝前のながらスマホは危険です。ブルーライトが睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑え、深い眠りを妨げます。結果的に寝ても疲れが取れない状態につながります。
ながらスマホをやめるメリット
- 集中力が高まる
- 食事や読書がより「味わえる」
- 睡眠の質が改善する
- 脳疲労が減り、日中のパフォーマンスが向上する
「ただやめる」だけで、これだけの恩恵があります。
今日からできる!ながらスマホのやめ方
1. スマホの“置き場所”を変える
- 食卓や作業机の上ではなく、少し離れた棚に置く。
- 「手の届かない場所にある」というだけで触る回数は大幅に減ります。
2. 通知をオフにする
- SNSやニュースアプリの通知をオフにすることで、無駄な“呼びかけ”が減ります。
- 必要な連絡は電話やメッセージのみ残すのがおすすめです。
3. アプリ使用時間を制限する
- iPhoneの「スクリーンタイム」やAndroidの「Digital Wellbeing」を活用。
- 1日○分までと決めて、自分で制御する仕組みを導入します。
4. 食事・読書の“ながら禁止ルール”をつくる
- 「ご飯のときはスマホを触らない」
- 「読書中は通知を切る」
といった明確なルールを決めることで、習慣化しやすくなります。
5. スマホ以外の“癒し”を用意する
- リラックスしたいときは散歩やストレッチに切り替える。
- 寝る前はアロマや音楽など、デジタルに頼らない習慣を取り入れましょう。
まとめ
“ながらスマホ”は便利なようでいて、実際には脳を疲れさせ、生活の質を下げる習慣です。
今日からできる小さな工夫——「置き場所を変える」「通知を切る」「ルールを作る」——を積み重ねることで、集中力と心の余裕を取り戻せます。
脳疲労を減らし、より健やかな毎日を過ごすために、まずは1つ行動を変えてみませんか?

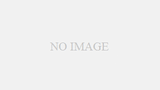
コメント